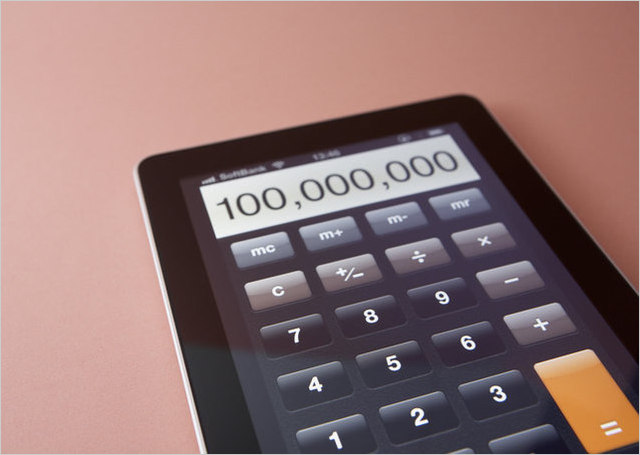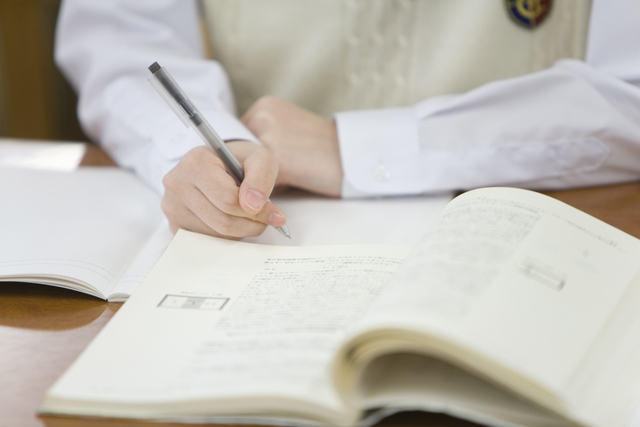財団医療法人の機関
財団医療法人の機関

財団医療法人には、評議員会、理事、理事会、監事を置かなければいません。
最高意思決定機関として評議員会、業務執行機関として理事会、監査機関として監事という役割となります。
評議員会
評議員会とは

評議員会とは、財団医療法人の評議員で構成される諮問機関であり、最高意思決定機関です。医療法人に関する重要な決定事項については、評議員会で決めることになります。
評議員会で決議内容は、医療法で決められた事項や寄附行為で定められた事項となります。理事・監事の選任・解任や寄附行為変更などです。
評議員会の種類

評議員会には、「定時評議員会」と「臨時評議員会」があります。
定時評議員会は、年1回は必ず開催しなければいけません。
臨時評議員会は、理事長が必要と判断した場合に招集されます。また総評議員の5分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して、臨時評議員会の招集を請求された場合には、理事長はその請求のあった日から20日以内に臨時評議員会を招集しなければいけません。
評議員会の決議

評議員会の決議は、医療法に別段の定めがある場合を除き、総評議員の過半数が出席し、出席した評議員の議決権の過半数で決することになります。
評議員は、1人1個の議決権を持っています。議決事項について、特別の利害関係を有する者は、議決権を行使することができません。
評議員会で決議する内容によっては、下記のとおり医療法やモデル寄附行為によって決議要件が異なります。
・「財団医療法人の解散」
→ 総評議員の3分の2以上の賛成
・「合併」「分割」
→ 総評議員の3分の2以上の賛成
・「監事の解任」
→ 出席評議員の議決権の3分の2以上の賛成
評議員会の議事録

評議員会の議事については、議事録を書面又は電磁的記録により作成しなければいけません。評議員会議事録の記載事項は次のとおりです。
(1)評議員会が開催された日時及び場所
(2)評議員会の議事の経過の要領及びその結果
(3)決議を要する事項についての特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名
(4)一定の事項における監事の評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
(5)評議員会に出席した評議員、理事又は監事の氏名
(6)評議員会の議長の氏名
(7)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
理事
理事とは

理事とは、医療法人の業務執行の意思決定を行う理事会の構成員のことをいいます。
医療法人は、原則理事を3人以上置かなけれなりません。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人でもよいとされています。
理事の要件

医療法人の理事は、必ずしも医師、歯科医師でなければいけないことはありませんので、医師や歯科医師でない者も理事になることができます。
また医療法人の管理者は原則として、理事に就任しなければいけません。医療施設に必要な管理者の意向を医療法人の運営に正しく反映させるためです。
ただし、下記に該当する場合は、理事に就任することはできません。
① 法人
② 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
③ 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
④ ③に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
理事長
理事長とは

理事長とは、医療法人の代表し、医療法人の業務に関する一切の行為をする権限を有しています。
理事長は理事会において、理事の中から選出されます。
理事長は、原則として、3か月に1回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければいけません。この報告は、現実に行われた理事会において報告しなければならず、省略することはできません。
理事長の資格等

医療法人の理事長は、原則として医師又は歯科医師である理事から選出しなければいけません。医療法人を代表する者による医学的知識の欠落に起因する問題が惹起されることを未然に防止するためです。
ただし、例外として一定の要件を満たせば、都道府県知事の認可を受けることにより、医師や歯科医師でなくても理事長の子女や長期間勤務している理事などが理事長になることもできます。
また医療法人の理事長が他の医療法人の理事長に就任することについては、特に禁止されていません。ただし他の医療法人の理事長になる特別な理由、必然性がなければならないとされています。
理事会
理事会とは

理事会とは、理事で構成される医療法人の業務執行機関です。
医療法人の業務を決定します。また理事の職務執行を監督し、理事長を選出、解職する権限を持っています。
理事会の決議

理事会は、議決に加わることができる理事の過半数(寄附行為で過半数を上回る定めも可。)が出席し、出席した理事の過半数の賛成で決します。
理事は、1人1個の議決権を持っています。決議事項に特別の利害関係を有する者は、議決権を行使することはできません。
理事会で決議する内容によっては、主に次のような事項となっております。
・基本財産の処分
・収支予算の決定
・重要な資産の処分、譲受
・多額の借財
・剰余金又は損失金の処理
理事会の議事録

理事会の議事については、議事録を書面又は電磁的記録により作成しなければいけません。理事会議事録の記載事項は次のとおりです。
(1)理事会が開催された日時及び場所
(2)理事等により理事会が招集されたときはその旨
(3)理事会の議事の経過の要領及びその結果
(4)決議を要する事項についての特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
(5)一定の事項における理事会において、述べられた意見又は発言ががあるときは、その意見又は発言の内容の概要
(6)理事会の議長の氏名
監事
監事とは

監事は、医療法人の監査機関として、次の職務を行います。
(1)医療法人の業務を監査すること
(2)医療法人の財産の状況を監査すること
(3)医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3ヵ月以内に評議員会及び理事会に提出すること
(4)監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事、評議員会又は理事会に報告すること
(5)(4)の報告をするために必要があるときは、評議員会を招集すること
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案等を調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること
監事の要件等

監事は、理事の業務を監督する立場なため、その医療法人の理事や職員などを兼ねることはできません。
また医療法人の理事の親族や取引関係、顧問関係にある人も監事になれません。
まずはお気軽に解散のこと、ご相談ください

お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。