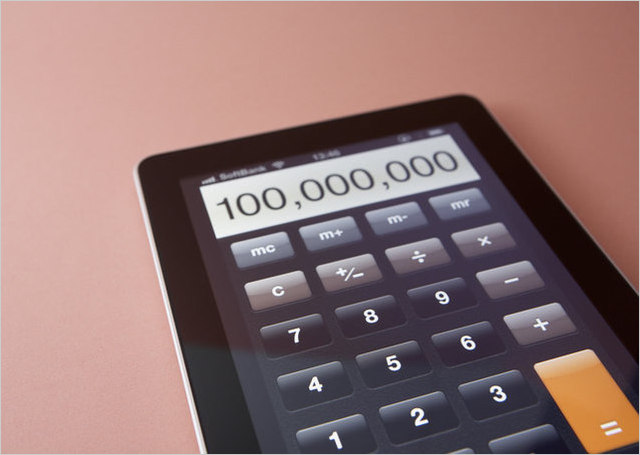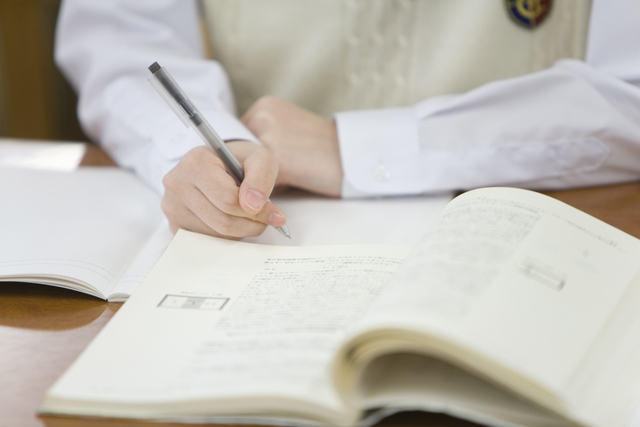残余財産の処分(医療法人)

残余財産とは、解散した医療法人が現務を結了し、債権と取立て、債務を弁済したのち、なお医療法人に残っている財産のことをいいます。
医療法人に財産を残したままでは、医療法人を消滅させることはできませんので、残余財産は処分する必要があります。
残余財産の処分(帰属先)について、医療法では
1 解散した医療法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
となっています。
各医療法人の残余財産の処分
持分あり医療法人(経過措置医療法人)

医療法の改正により現在は、設立することができなくなった持分の定めのある医療法人(経過措置医療法人)ですが、モデル定款では次のように定められています。
「本社団が解散した場合の残余財産は、払込済出資額に応じて分配するものとする」
出資した額が残余財産となるわけではなく、他の出資者の出資額との割合により処分されることになりますので、出資額よりも多くなることも少なくなることもあり得ます。
出資額限度法人

経過措置医療法人の一種である出資額限度法人も現在は設立することはできなくなりました。残余財産の処分についてモデル定款では次のように定められています。
「本社団が解散した場合の残余財産は、払込済出資額を限度として分配するものとし、当該払込済出資額を控除してなお残余があるときは、社員総会の議決により、〇〇県知事(厚生労働大臣)の認可を得て、国若しくは地方公共団体又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の2に定める特定医療法人若しくは医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2に定める社会医療法人に当該残余の額を帰属させるものとする。」
出資した者は、出資した額以上の財産が分配されることはありません。残余財産の額が出資額合計よりも少ないときは、各出資者の分配額は、出資額よりも少なくなることはあり得ます。
持分なし社団医療法人

持分の定めのない社団医療法人についてのモデル定款の解散の規定は、
(1)国
(2)地方公共団体
(3)医療法第31条に定める公的医療機関の開設者
(4)都道府県医師会又は群市区医師会(一般社団法又は一般財団法人に限る。)
(5)財団たる医療法人又は社団たる医療法人であって持分の定めのないもの
とされています。
医療法上「残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であって厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない」
とされているため、社員に残余財産を処分することはできません。
基金拠出型法人

基金拠出型法人は持分の定めのない社団医療法人ですので、解散に関する定めについては、
(1)国
(2)地方公共団体
(3)医療法第31条に定める公的医療機関の開設者
(4)都道府県医師会又は群市区医師会(一般社団法又は一般財団法人に限る。)
(5)財団たる医療法人又は社団たる医療法人であって持分の定めのないもの
とされています。基金制度を採用していることによって解散に関する定めについて違いがあれうわけではありません。
財団医療法人

財団医療法人の解散に関する定めについては、モデル寄附行為では、持分の定めのない社団医療法人同じです。
(1)国
(2)地方公共団体
(3)医療法第31条に定める公的医療機関の開設者
(4)都道府県医師会又は群市区医師会(一般社団法又は一般財団法人に限る。)
(5)財団たる医療法人又は社団たる医療法人であって持分の定めのないもの
特定医療法人

特定医療法人は解散に関する定めについては、租税特別措置法、租税特別措置法施行令の基準で、「解散に際して残余財産が国若しくは地方公共団体又は財団たる医療法人又は持分の定めのない社団医療法人の帰属する旨」が必要とされています。モデル定款(寄附行為)では、
「本社団(財団)が解散したときの残余財産は、国若しくは地方公共団体又は同種の医療法人に帰属せしめるとする。」
とされており、他の医療法人よりも限定的な定めとなっています。
社会医療法人

社会医療法人の解散に関する定めについては、医療法42条の2第1項第7号により「解散に際して残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属させる旨」が必要となります。
特定医療法人と同様限定的な定めを置いています。
まずはお気軽に解散のこと、ご相談ください

お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。