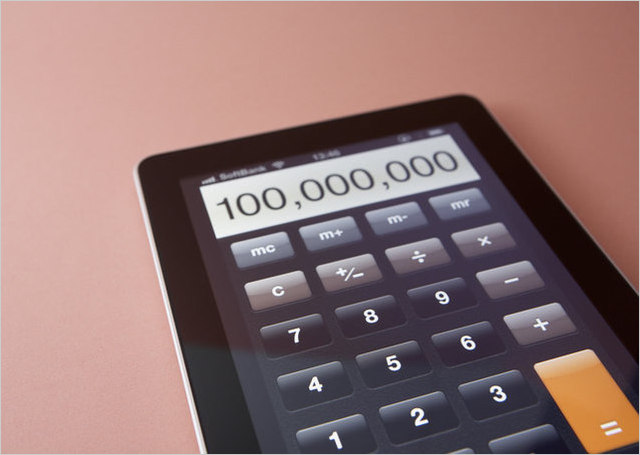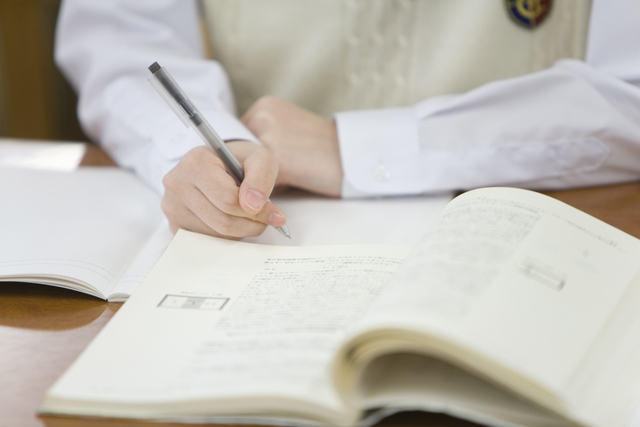社会福祉法人の機関
社会福祉法人の機関

社会福祉法人には、評議員会、理事、理事会、監事を置かなければいません。また定款で定めることにより、会計監査人を置くことができます。
業務執行機関として理事会、法人運営の重要事項の議決機関としての評議員会、監査機関として監事、計算書類等を監査する会計監査人という役割となります。
理事
理事とは

理事とは、社会福祉法人の業務執行の意思決定を行う理事会の構成員のことをいいます。
社会福祉法人は、原則理事を6人以上置かなけれなりません。社会福祉法人の理事は、会社の役員と同じように、善管注意義務、忠実義務を負います。
理事の要件

社会福祉法人の理事は、
① 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
② 当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
③ 当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあっては、当該施設の管理者
を含めなければいけません。
また各理事について、親族等特殊関係者が3名を超えて含まれてはならず、かつ理事総数3分の1を超えてはいけません。
理事の欠格事由

下記の者は、社会福祉法人の理事になることができません。
① 法人
② 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
③ 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又は社会福祉法の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
④ ③を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
⑤ 解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
理事会
理事会とは

理事会とは、理事で構成される社会福祉法人の業務執行機関です。
社会福祉法人の業務を決定します。また理事の職務執行を監督します。
理事会を招集するのは、理事長ですが、社会福祉法人の業務等に関して不正等があった場合、監事は理事長に対して、理事会の招集を請求できます。
理事会の決議

理事会は、理事長が招集し、議長となります。議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数の賛成で決します。
理事会には、代理出席や書面表決は認められず、理事本人の出席しなければなりません。
理事は、1人1個の議決権を持っています。決議事項に特別の利害関係を有する者は、議決権を行使することはできません。
監事
監事とは

監事は、社会福祉法人の監査機関として、次の職務を行います。
(1)社会福祉法人の業務を監査すること
(2)社会福祉法人の財産の状況を監査すること
(3)理事の業務執行の状況を監査すること
(4)社会福祉法人の業務又は財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2ヵ月以内に評議員会及び理事会に提出すること
(5)監査の結果、社会福祉法人の業務又は財産又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを所轄庁、評議員会又は理事会に報告すること
(6)(5)の報告をするために必要があるときは、理事会及び評議員会を招集すること
(7)社会福祉法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意見を述べること
監事の要件等

監事は、評議員会の決議により選任します。
監事のうち、次に掲げる者を含めなければいけません。
① 社会福祉事業について見識を有する者
② 財務管理について見識を有する者
監事は、理事の業務を監督する立場なため、その社会福祉法人の理事又は職員などを兼ねることはできません。
監事の欠格事由

下記の者は、社会福祉法人の監事になることができません。
① 法人
② 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
③ 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又は社会福祉法の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
④ ③を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
⑤ 解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
評議員
評議員とは

評議員とは、社会福祉法人の業務運営が適切に行われるよう役員の選任、解任の権限を通じ事後的に法人運営を監督する者をいいます。
評議員は、理事の定数を超える数を置くことが必要で、社会福祉法人の適正な運営に必要な見識を有する者のうちから、定款で定めるところにより選任します。社会福祉法人の適正な運営に必要な見識を有する者とは、民生委員や地域住民のためのボランティア活動をしている者などをいいます。
評議員の欠格事由

下記の者は、社会福祉法人の評議員になることができません。
① 法人
② 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
③ 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又は社会福祉法の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
④ ③を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
⑤ 解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
また、評議員は、役員を監督する立場であるので、当該社会福祉法人の役員や職員を兼ねることはできません。
評議員会
評議員会とは

評議員会とは、社会福祉法人の評議員で構成される合議制の機関で、社会福祉法人の重要な事項の決定に関する機関です。
以前は社会福祉法人において評議員会は任意の諮問機関でしたが、社会福祉法人が改正され必須の機関となりました。
評議員会は法人の基本ルールの決定とともに、理事に関する選任、解任の権限を持つことで、法人運営を監督する役割を果たします。
評議員会の運営

評議員会は、毎会計年度終了後一定の時期に招集する「定時評議員会」と必要がある場合に招集する「臨時評議員会」があります。評議員会は理事が招集します。
評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合は、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行います。
ただし、次の決議については、議決に加わることができる評議員の3分の2以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上にあたる多数をもって行わなければいけません。
1 監事の解任
2 役員の責任の一部免除
3 定款変更
4 解散
5 吸収合併、新設合併
まずはお気軽に解散のこと、ご相談ください

お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。