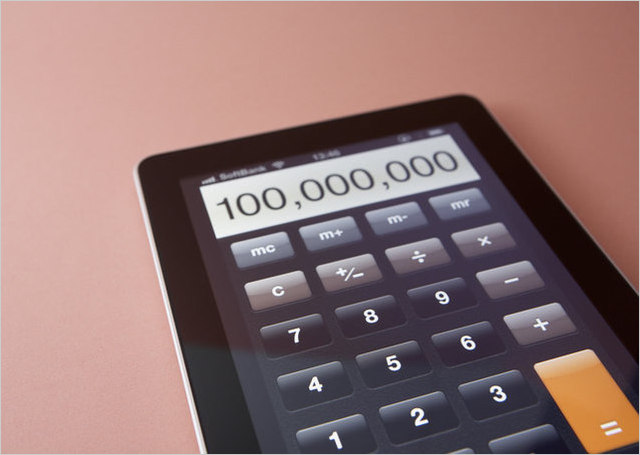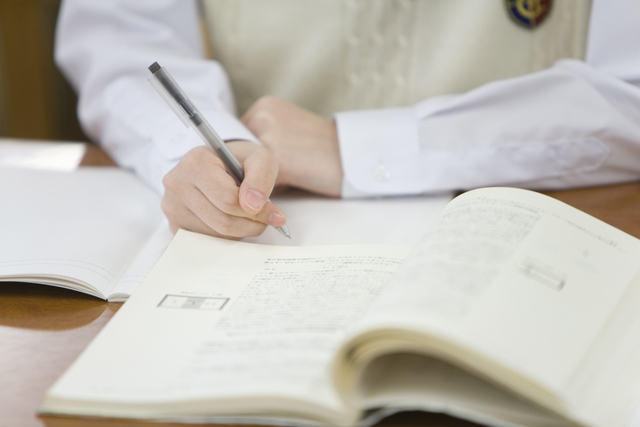清算人とは・・・

清算人とは、清算中の一般財団法人において、業務の執行を行う者のことをいいます。解散前に業務執行していた理事に代わって清算人が業務を執行していくことになります。
清算人も理事と同様、委任に関する規定に従うものとされています。理事と同じように、清算人は清算会社に対して、忠実義務、競業避止義務、利益相反取引の制限等を負います。
➡ 清算人の登記についてはこちら
清算人の選任
評議員会の決議により選任
評議員会で清算人を選任することができます。解散前の理事以外の者を清算人にすることも、理事のうち一部の者を清算人に選任することもできます。実務的に多いのがこの方法での選任です。
定款の定めによる清算人
あらかじめ定款で一般財団法人が解散したときの清算人を定めておくことができます。原始定款で定めておくこともできますし、途中で定款変更して定めることも可能です。実務上そのような定めを置いている会社はあまり見受けられません。
法定清算人
評議員会の決議で選任された者又は定款で定める者がいない場合、従前の理事が清算法人の清算人になります。これを「法定清算人」といいます。上記に該当する場合は、特に評議員会の決議等の手続をすることなく、従前の理事が当然に清算人になります。また代表理事だったものは、当然に代表清算人になります。
清算人の職務
清算人は、次の職務を行います。
会社財産の現況調査
清算人は、就任後遅滞なく、清算法人の財産の状況と調査し、清算の開始原因が生じた日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければいけません。
➡ 財産目録等の作成について
現務の結了
現務の結了とは、解散時にまだ終わっていない残務を終了させることをいいます。たとえば、残った在庫の売却、締結済みの契約の履行などです。
債権の取立て及び債務の弁済
債務の弁済や残余財産の分配を行う上で、法人財産を換価しておく必要があります。一般社団法人がもっている債権については、債務者からその履行を受けます。会社が負担している債務についても弁済をします。ただし、債権者へ随時弁済することはできず、債権者への公告と各別の催告期間を経て、弁済を行います。
➡ 債務の弁済について
残余財産の帰属
法人財産を換価し、債権者に債務を弁済してもなお残余の財産がある場合、定款の定めるところにより、残余財産を帰属させます。
清算人の資格
清算人は、理事と同じように欠格事由があります。
欠格事由
- 法人
- 会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の一定の法律など、会社関連の法律に定められた罪によって刑に処せられその執行を終わった日から2年を経過していない者
- 上記法律以外の罪によって禁固以上の罪に処せれられその執行を終わるまでの者
清算人の義務等
清算人と一般財団法人との関係は、理事と同じように委任に関する規定に従います。よって理事と同じ次のような義務を負います。
忠実義務
清算人は、一般財団法人に対して、忠実にその職務を行う義務を負います。法令、定款並びに評議員会の決議を順守し、一般財団法人の為に、職務を行わなければなりません。
競業避止義務
清算人は、自己又は第三者のために一般財団法人の事業の部類に属する取引をしようとするときは、一般財団法人の承認を受けなければいけません。
解散後であっても現務の結了の過程で、一般財団法人の利益を害する可能性があるためです。
利益相反取引
清算人は、自己又は第三者のために一般財団法人と取引をしようとするときは、一般財団法人の承認を受けなければいけません。
競業避止義務と同じように、解散後であっても現務の結了の過程で、一般財団法人の利益を害する可能性があるためです。
報告義務
清算人は、一般財団法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、ただちにその事実を評議員(監事設置清算法人については、監事)に報告しなければいけません。
清算人の報酬
清算人の報酬については、定款に定めがない場合は、評議員会において決定することになります。理事と同様です。
具体的には、理事が受ける報酬、賞与その他職務執行の対価として受ける財産上の利益について
① 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
② 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
③ 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
を評議員会の決議によって定めます。
清算人の責任
清算人は理事と同じように一般財団法人に対して義務を負っていますので、それを怠ったときは責任を負うことになります。
任務懈怠責任
清算人は、清算法人との関係は、委任に関する規定に従うとされていますので、一般財団法人に対して、忠実義務を負っています。清算人は、任務を怠ったときは、清算法人に対して、任務懈怠により生じた損害を賠償する責任を負います。
競業避止、利益相反取引の制限
清算人は、競業取引や利益相反取引をしようとする場合は、評議員会においてその承認を受けなければいけません。それに違反して取引をしたときは、当該取引によって清算人又は第三者が得た利益の額が損害額として推定されます。
第三者に対する責任
清算人は、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があった場合は、当該清算人はこれによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います。
まずはお気軽に解散のこと、ご相談ください

お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。