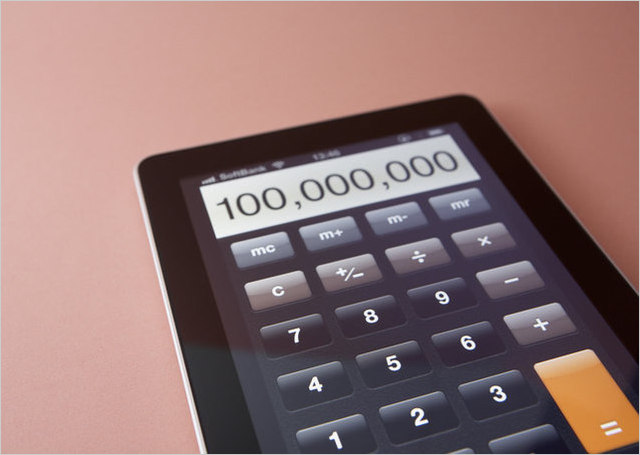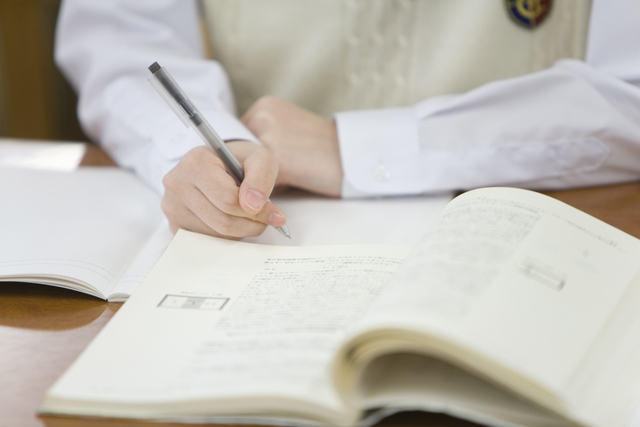規則(宗教法人)について

宗教法人おける「規則」とは、会社でいう「定款」のようなもので、その宗教法人の目的、組織、管理運営など根本原則を定めたものをいいます。いわば宗教法人の憲法のようなものです。
宗教法人は常に法令、規則に従い業務運営を図るとされています。
宗教法人の規則は、設立時に必ず作成されます。そして所轄庁の認証が必要になります。
規則の記載事項
規則には、下記の事項が記載されます。
目的
宗教法人は、「法定の規定に従い、規則に定める目的の範囲内で権利を有し、義務を負う」とされているところ、具体的にどのような目的を達成するために宗教法人で事業を行うかを記載します。
たとえば、〇〇宗の教義を広め、法要儀式を行い、信者を教化育成すること、などです。
名称
宗教法人の名称を記載します。「○○寺」であれば、規則上は、「宗教法人○○寺」ではなく、宗教法人「○○寺」となり、「宗教法人」の文言は、登記簿上も載ってきません。
事務所の所在地
事務所が所在する場所を記載します。株式会社のように最少行政区画までの記載でも大丈夫ですが、通常は、○○県○○市○○町○○番地のように最後まで記載します。
設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合は、その名称及び宗教法人非宗教法人の別
神社、寺院、教会など多くは、教派、宗派、教団などに属しています。設立しようとする宗教団体に、属している「包括宗教団体」があれば記載します。
各役員についての呼称、資格及び任免並びに代表役員については、その任期及び職務権限、責任役員についてはその員数、任期及び職務権限、代務者については、その職務権限に関する事項
宗教法人の役員について、規則で広く資格や任免方法、員数等を決めます。特に職務権限については、必ず記載しなければいけないのが他の法人にはない特徴です。
議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関する事項
宗教法人の意思決定をする「議決」機関だけでなく、意思決定をするうえで意見を伺う「諮問」機関や適正な財務運営を図るためのチェック機関としての「監査」機関を置く場合は、規則でその旨を定めます。総代会や監事などです。
公益事業を行う場合には、その種類及び管理運営に関する事項
宗教法人が公益事業や公益事業以外の事業を行う場合は、規則に定めなければいけません。公益事業とは、教育や福祉に関する事業などをいいます。
基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分、予算、決算及び会計その他財務に関する事項
基本財産の設定の仕方やそれらの処分についての方法など宗教法人における財産関係について、規則で定めます。特に財産の処分については、宗教法人の財政基盤にかかわる重要な事柄なので、広く意見を聴いたうえでの処分方法としている例が一般的です。
規則の変更に関する事項
規則に定めたことについて変更をする場合の手続きについては、法律上の決まりはなく、規則に変更方法を定めるとしています。
ただし、規則の変更には、規則に定めた方法と所轄庁の認証をもってその効力を生じます。
解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合には、その事項
解散の事由については、法律上決めれられていますが、任意解散の場合の手続きについては、規則で定めます。また残余財産の帰属についても、通常は規則で定めておきます。
公告の方法
宗教法人が重要な行為をしようとする場合は、広くその旨を信者等に知らせるために、その方法を規則で定めなければいけません。新聞、機関紙等発行する紙面や事務所の掲示場に掲示するなどが一般的です。
他の宗教団体によって制約される事項
宗教法人の包括団体である教派、宗派、教団当から受ける制約事項がある場合は、その定めも規則で定めます。
規則の認証

規則は認証が必要です
宗教法人を設立しようとする者は、規則を作成し、所轄庁の認証を受けなければいけません。
宗教法人の所轄庁とは、当該宗教法人の所在地の都道府県知事となりますが、他の都道府県に境内建物を有する場合、当該宗教法人を包括する宗教法人、または他の都道府県にある宗教法人を包括する宗教法人の所轄庁は文部科学大臣となります。
規則の変更

変更にも認証が必要です
宗教法人の規則を変更するには、規則に定めた変更のための手続きが必要です。たとえば、総代会、責任役員会における決議や包括団体の承認などとなります。さらに規則の変更についても所轄庁の認証をうけなければなりません。
規則の内容で、被包括関係の設定や廃止に係る変更をしようとするときは、規則の変更の認証申請の少なくとも2か月前に、信者その他の利害関係人に対し、当該規則の変更の案の要旨を示してその旨を公告しなければいけません。
まずはお気軽に解散のこと、ご相談ください

お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。