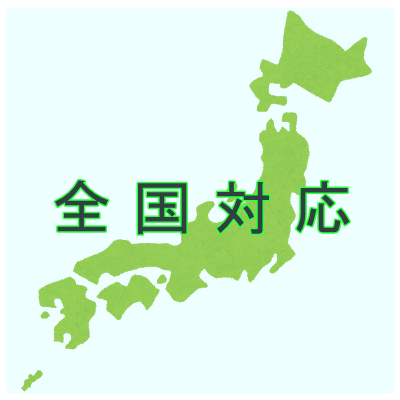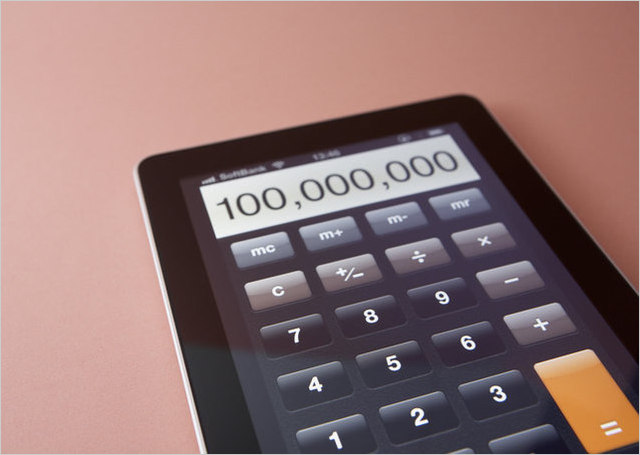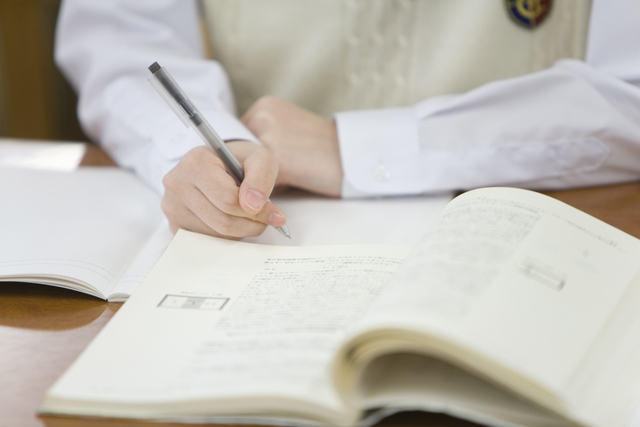会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

会社解散手続きはすべてお任せください。
運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
解散、廃業、清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。
受付時間:9:00〜18:00
土日祝日対応可(要事前予約)
お気軽にお問合せください
0120-313-844
社長の相続における遺産分割のポイント

社長が亡くなった際の相続では、単なる個人資産の分割だけでなく、会社経営に関わる資産の扱いも重要なポイントとなります。特に、自社株や個人の所有だが事業で使ってい資産(事業用資産)の分割方法を誤ると、会社の存続や経営の安定性が損なわれる可能性があります。
遺産分割の基本とスムーズな相続のための対策を知ることによって、揉めない円満な相続を実現することができます。
遺産分割とは
遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)が残した財産を相続人間でどのようにわけるかを決めることをいいます。
被相続人が残した財産について、遺言がない場合は、この遺産分割が整うまで相続人全員で「共有」している状態となります。この共有という状態は、他の相続人の同意がないと売却や活用ができないので、手続きが停滞する原因になります。
遺産分割の話し合いがまとまらない場合は
遺産分割は相続人の全員がその協議の内容に同意する必要があります。一人でも協議の内容に納得ができず、同意しない場合は、遺産分割の協議は成立しません。
遺産分割調停

遺産分割調停とは、相続人間での話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所において第三者(調停委員)の仲介のもとで、分割の方法を決める手続きのことをいいます。
公平な第三者が間に入ることで、冷静な話し合いができるメリットがありますが、そもそも相続人の一部が参加しなかったり、ここでも合意できない場合は最終的に審判に進む可能性もあります。
遺産分割審判

遺産分割審判とは、遺産分割調停が不成立となった場合に、家庭裁判所が相続財産の分割方法を決定する手続きのことをいいます。
最終的に裁判所が法的に判断をするので、公平な決定が得られます。拒否する相続人がいても実行できますので、最終的な解決になります。
遺産分割の方法
遺産分割には、4つの方法があります。
現物分割

現物分割とは、相続財産を相続人間で物理的に分ける方法のことをいいます。
「A土地」は相続人〇〇が、「B建物」は相続人△△が相続するといったように、物理的に分けることが可能な相続財産については、現物分割をすることが可能です。ただ、各相続人の相続分どおりに分けることは実際には難しいため、他の分割方法も併用して行います。
換価分割

換価分割とは、相続財産を売却して現金化し、現金で分ける方法のことをいいます。現物分割では難しく取得希望者がいない場合や相続分どおりに分けたい場合に利用されます。ただ売却に時間や費用がかかってしまうというデメリットがあります。
代償分割

代償分割とは、相続財産のうち特定の財産を一部の相続人が取得し、その代わりに他の相続人に対して金銭を支払う方法のことをいいます。
現物分割を補完する方法として相続人間の公平性が保て、資産を売却しなくて済むというメリットがありますが、代償金を支払う相続人がまとまった資金を用意する必要があります。
共有分割

共有分割とは、相続財産を相続人が共有で分割する方法のことをいいます。
売却が難しい資産などに用いられることをが多く、共有した相続人が共同で管理、利用していくことになります。共有という状態は、管理、運用が難しくトラブルの原因にもなりやすいため、慎重な検討が必要になります。
遺産分割の流れ
遺産分割の一般的な流れをご説明いたします。
遺言書の有無の確認

まずは被相続人が遺言書を残していないかを確認しましょう。遺言書がある場合は、遺産分割よりも遺言書が優先されるため、遺言書に基づいて財産を分けることになります。
遺言にはいくつか種類があるため、その種類によっては内容が正当かどうか判断する必要があります。
相続人の確定

遺産分割は相続人全員で行う必要があります。関与を拒否している相続人や連絡の取れない相続人などを無視して遺産分割することはできません。
一同に会して協議を行うことは必ずしも必要ありませんが、相続人一人でも欠けるとその遺産分割協議は無効になります。
相続財産の確認

相続人が確定できれば、相続人間でどの財産を分けるのかを確認する必要があります。被相続人が残したプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めて全財産を把握することが重要です。一部の財産が漏れていても遺産分割協議として無効となるわけではありませんが、後日の紛争とならないようもれなく把握することが望ましいです。
遺産分割協議の実施

相続人全員で、遺産分割協議を行います。必ずその場に全員いる必要はなく、書面でのやり取りを交えての協議も可能です。
分割の内容として各相続人の法定相続分をもとに分割するのが多いですが、相続人全員が合意すれば、法定相続分どおりに分ける必要はありません。
話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
相続財産の名義変更など

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書をもとに各相続財産の名義変更等を行います。
預貯金の解約、分配や不動産や株の名義変更などを行います。
各相続人に財産が承継されると、遺産分割は完了となります。
社長の相続における遺産分割の課題
自社株の分散による経営権の不安定化

社長の保有する自社株を法定相続分どおりに分割すると、後継者が会社の支配権を確保できず、経営の安定性が損なわれるリスクがあります。
対策として、後継者に株式を集中させる遺言を作成することや生前贈与や種類株式を活用し、後継者の株式保有割合を高めるなどの方法があります。
役員貸付金、借入金の取扱い

社長が会社に対してお金を貸している「役員借入金」社長が会社からお金を借りている「役員貸付金」については、社長個人の相続財産とされ、遺産分割の対象になります。
会社経営にも相続人間の分割にも影響しますので、生前に精算をするなど、遺言や保険などで対策をする必要があります。
事業用不動産の分割

社長の個人名義の不動産のうち、会社の事業経営で使用している不動産については、名義が個人であるので相続財産となり、遺産分割の対象になります。分割方法を誤ると、事業継続に支障をきたす恐れがありますので、事前の対策が必要です。
生前に法人名義に変更したり、不動産の共有状態を避けるために、後継者に単独相続させるための遺言を書くなどの方法があります。
まずはお気軽に解散のこと、ご相談ください

お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。
各種会社(法人)の解散
お問合せはこちら