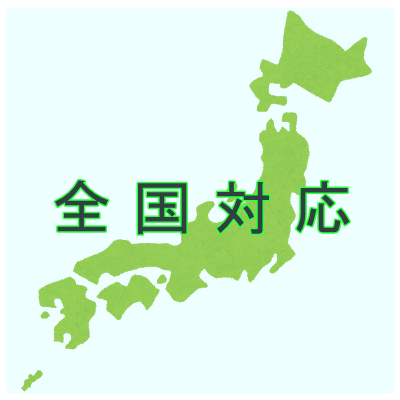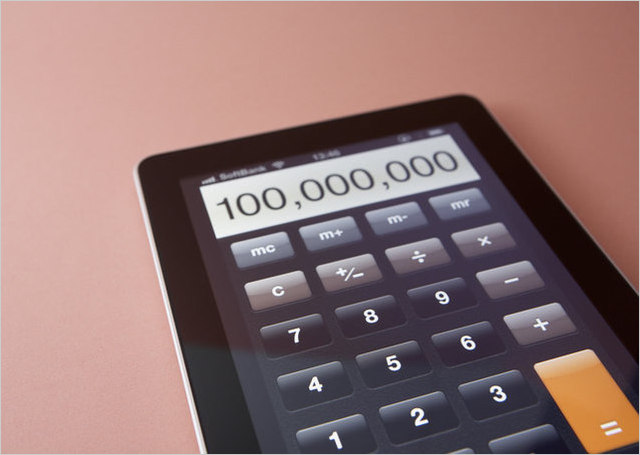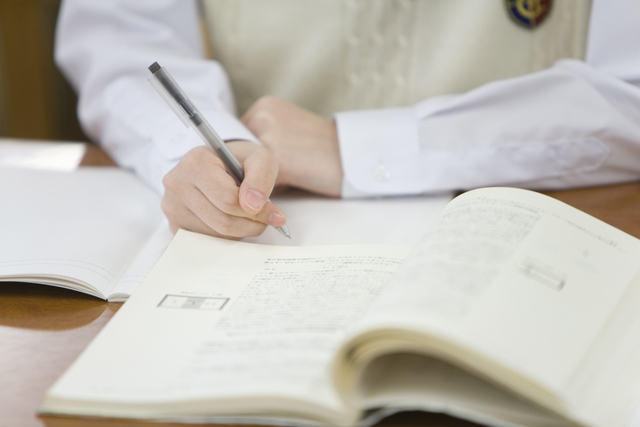会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

会社解散手続きはすべてお任せください。
運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
解散、廃業、清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。
受付時間:9:00〜18:00
土日祝日対応可(要事前予約)
お気軽にお問合せください
0120-313-844
社長の相続における遺言と相続対策

社長の相続は、個人の資産だけでなく会社の未来にも直結する重要な問題です。事前の対策が不十分だと、会社の経営が揺らぎ、家族間のトラブルにもつながります。特に会社の株式や事業承継について明確な指示をしておかないと、後継者の選定や相続税の負担、経営権の分散といった様々なリスクが発生します。
遺言の重要性
社長(代表取締役)が突然亡くなった場合、会社の株式は相続財産となります。何の準備もしていないと、法定相続分に従って相続され、株式が準共有とされてしまい、相続人間での遺産分割が必要になります。
遺産分割のデメリット

会社の株式を遺産分割協議によって、帰属先を決めるには相続人全員で協議をし、合意をしなければなりません。合意内容に一人でも反対する相続人がいると遺産分割協議は成立しません。
ですので、相続人間での合意形成が難しいと、解決するために争いに発展したりすることで、会社運営に支障が生じることがあります。
遺言のメリット

遺言書を作成することによって、株式の帰属先が明確になり、遺産分割協議がなくても、権利帰属者が決まります。
遺産分割協議などにより長期間にわたって紛糾するリスクがなくなるので、スムーズな事業承継が可能となります。
遺言の内容について
社長(代表取締役)が残すべき「遺言」ついては、会社のことだけでなく、相続人など親族のことも配慮した内容のものとすることが重要です。
自社株の承継

自社株については、できるだけ後継者に集中して承継させることが重要です。できれば100%後継者に相続させることが望ましいです。
社長の個人全体の財産のなかで、自社株が占める割合が高い場合、他の相続人の不平不満につながるので、生命保険を活用するなど対策が必要です。
遺留分への配慮

一般的に中小企業の社長の個人財産はその大半を自社株が占めていることが多く、後継者に自社株を承継させると、他の相続人の遺留分を侵害してしまいます。
他の相続人から遺留分減殺請求されてしまった場合は、後継者はその支払のために現金を用意する必要がありますので、注意が必要です。
遺言執行者の指定

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きをする人のことをいいます。遺言執行者の指定は、遺言の効力に影響を与えませんので、選任しなくても問題はありませんが、遺言の内容を確実に実行するために、信頼できる専門家(弁護士や司法書士など)を指定しておくことが好ましいです。
事業承継に関する指示

遺言において、後継者への具体的な引き継ぎ方法やスケジュールなど明確にすることも有益です。
会社のビジョンや方針を明文化することで、後継者が円滑に経営を進めるための指針となります。
遺言の主な種類
「遺言」ついては、法律で定められた形式があり、大きく分けで以下の3種類があります。
自筆証書遺言

社長がすべてを自筆で書き上げる形式の遺言です。最近の法改正により、財産目録についてはパソコンなどで作成が可能となり、使いやすくなりました。
費用がかからず、手軽に作成できる反面、形式不備で無効と判断されるリスクもあります。
また、その遺言で手続きをするには、家庭裁判所の検認が必要になります。
公正証書遺言

公証人が社長の口述に基づいて作成する遺言です。原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。また家庭裁判所の検認が不要で、確実性が高いといえます。
作成に費用がかかりますが、実務で利用されることが多く、法的な安心を求める方におすすめです。
秘密証書遺言

遺言は本人が作成し、封をしたうえで公証人に提出します。公証人と証人によって封印の事実が確認されますが、内容には立ち入りません。
遺言の内容を他人に知られたくない場合に用いられる方式です。自筆証書遺言と同様に検認が必要になります。実務上は利用されることは少ない方式です。
まずはお気軽に解散のこと、ご相談ください

お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。
各種会社(法人)の解散
お問合せはこちら